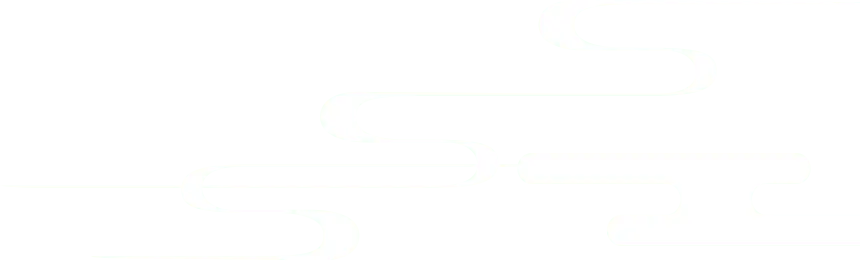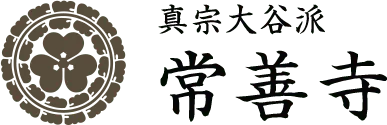常善寺について
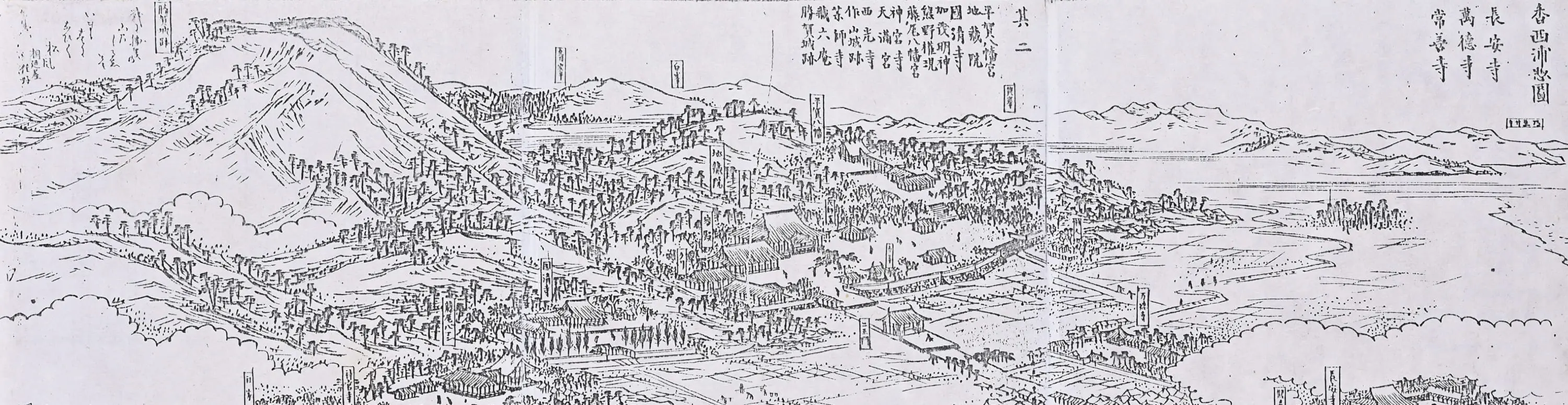
常善寺とは
甲来山・常善寺は
京都の東本願寺(真宗本廟)を
本山とする真宗大谷派の寺院です。
常善寺は高松駅から車で15分ほどの港町、香西の地にございます。
この地は古代から笠居郷とよばれ、香西の名は香川郡の西に位置することが由来と思われます。
嘉祥年間(848年〜851年)当地の守護に任じられた新居資村は香西氏と称しました。
香西氏は香川郡の西の笠居郷が本拠で佐料城を居城とし、勝賀山に勝賀城を築いた讃岐を代表する中世武士でございます。
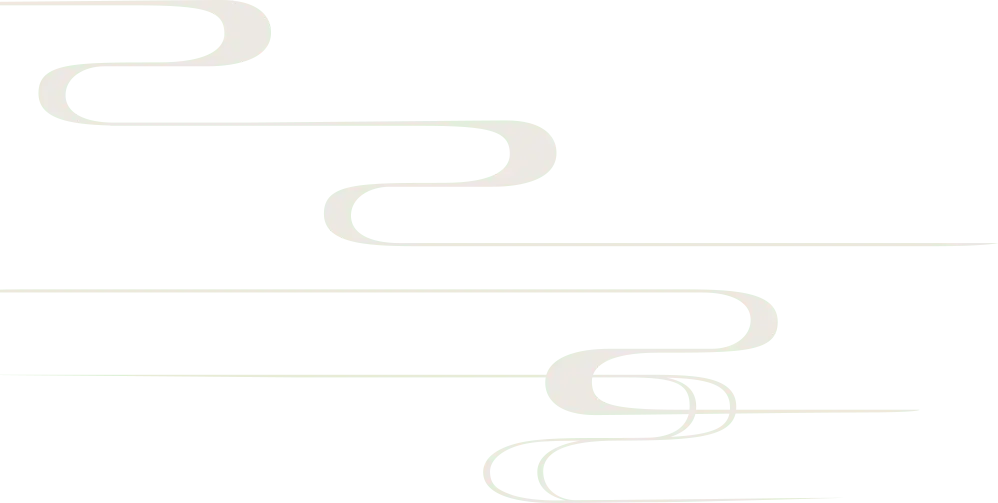
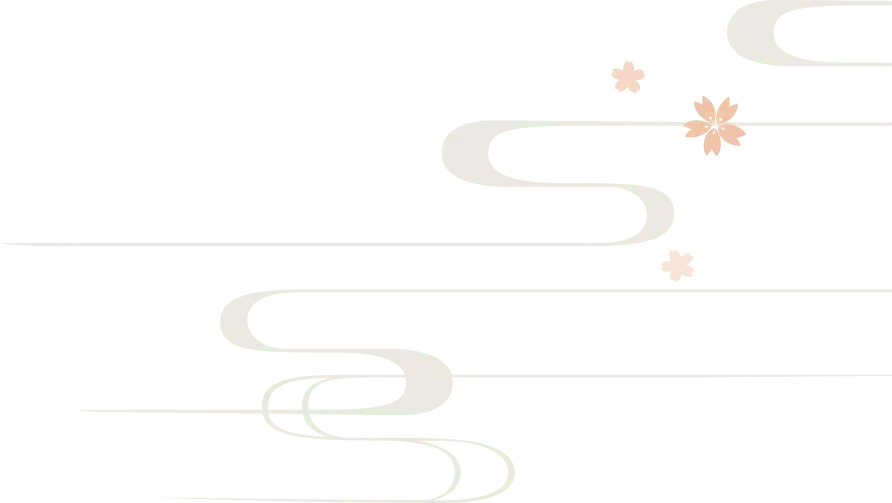


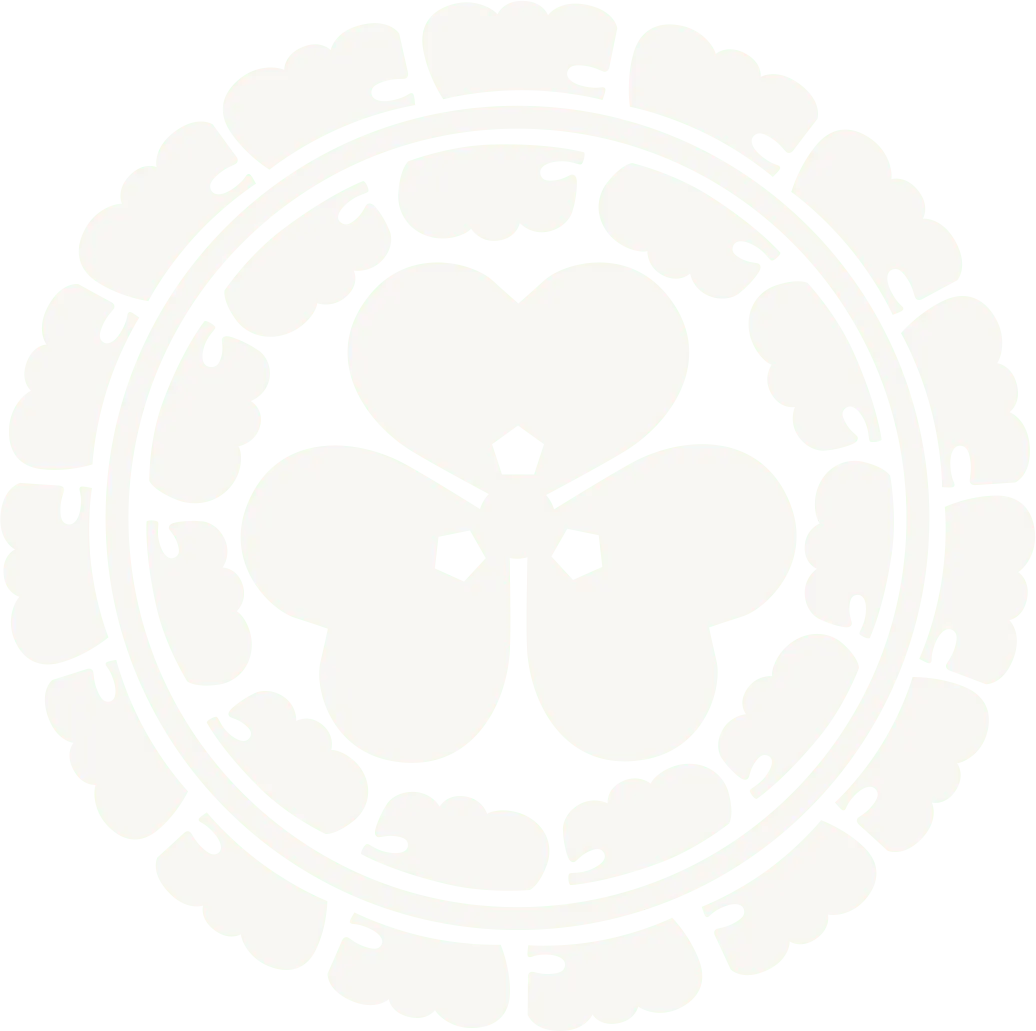
香西は鎌倉初期に香西氏によって開かれた町で、香西浦での漁業が盛んであり、有事にはそれらの漁夫が水軍として活躍しておりました。
天保7年(1836年)の「四国遍路道中雑誌」に香西浦は「人家凡千軒も有べし。農家漁家入接、綿并粉類を製す。少しの船間も有って随分繁華の場所にして、商戸多有の地なり」などと記されています。
香西の南東部には丸亀街道が通り宿場町もございました。
また、「香西はむきむきの町」といわれ、家々の向きが整然としておりませんでした。
これは中世、香西氏の水軍の要塞基地でもございましたので、道路は迷路のように袋小路やかぎ型に折れていて、角を曲がるたびに行き止まりや、突然海が見えたりいたします。
港に沿っては廻船問屋の大きな屋敷が今でも残っております。
常善寺はもともと甲斐長沢が開山の地でございます。
その後、御縁あって大永元年(1521年)にこの讃岐国香西に移ってまいりました。



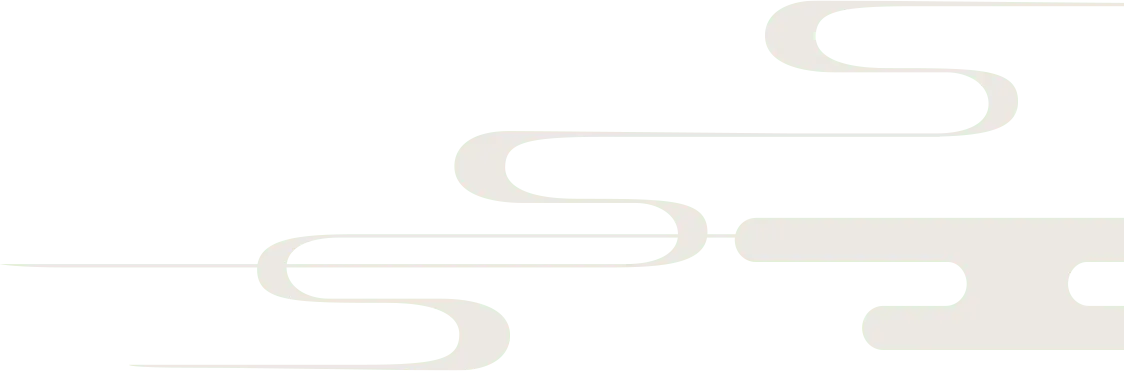
宗旨
| 本尊 | 阿弥陀如来 |
|---|---|
| 正依 の経典 |
仏説無量寿経
(
大経
)
仏説観無量寿経 ( 観経 ) 仏説阿弥陀経 ( 小経 ) |
| 宗祖 | 親鸞聖人 |
| 宗祖の主著 |
顕浄土真実教行証文類
( 教行信証 ) |
| 宗派名 | 真宗大谷派 |
| 本山 |
真宗本廟
(東本願寺)
京都市下京区烏丸通七条上る |