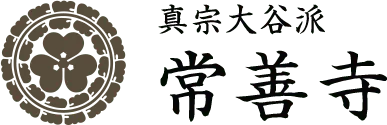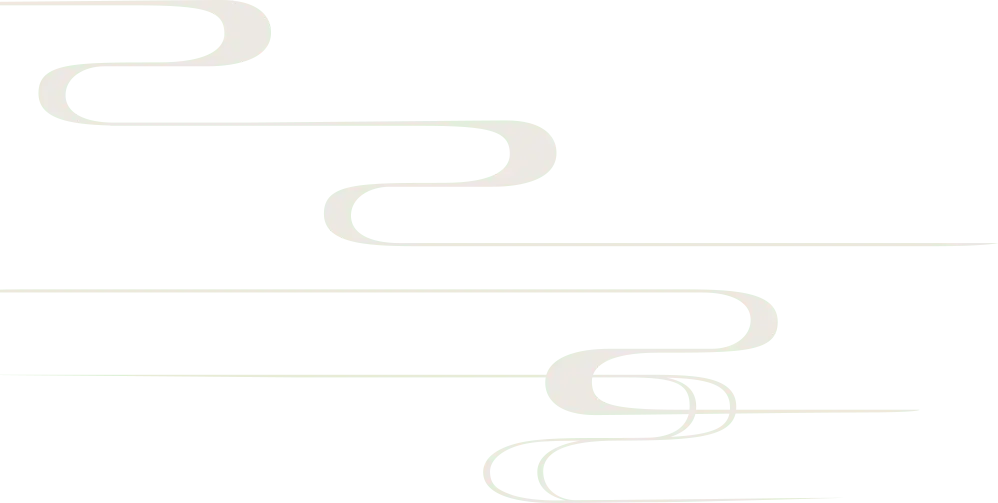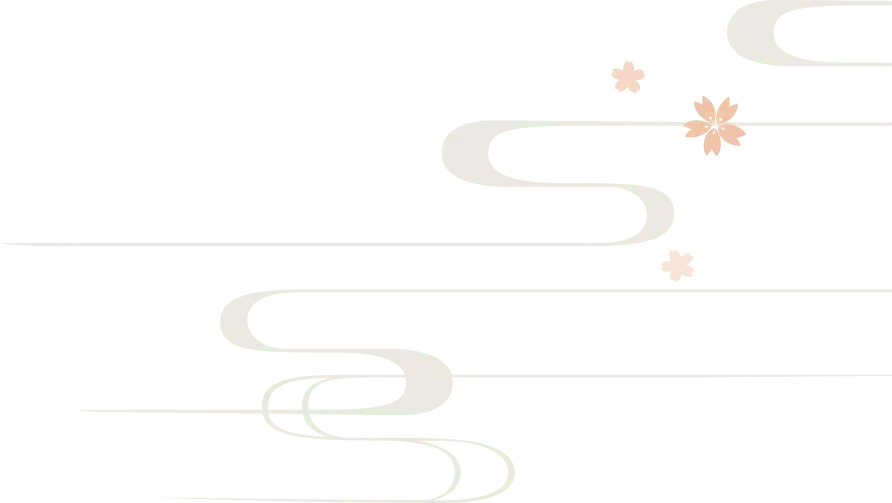盂蘭盆会
毎年八月になると、日本各地でお盆の行事が営まれます。この三連休からは実家に帰省される方も増え、お盆法要やご法事にお参りしますと、大変賑やかにお迎えいただくことが多くなりました。また、お寺の納骨堂にも、普段は香川を離れてなかなかお参りに来られない若い方々のお姿を、よくお見かけいたします。

お盆は正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といいますが、この言葉はサンスクリット語の「ウラバーナ(ullambana)」が音訳されたものです。もともとは「逆さにつるされたような苦しみ」という意味で、人が迷いの世界でどうしようもない苦しみにある姿をあらわしています。
『盂蘭盆経』には、目連尊者が餓鬼道に堕ちて苦しむ母を救おうとし、お釈迦さまに相談する場面があります。お釈迦さまは、目連尊者ひとりの力では母を救えないことを示され、夏安居を終えた多くの僧侶に、七月十五日に食事や衣を供養するよう教えられました。その功徳によって母が救われたことが、今日の盂蘭盆会のはじまりとされています。
真宗では、先に往かれた方を供養して救うのではなく、阿弥陀さまのはたらきによってすでに浄土へ往生された方のご縁を通し、私自身が阿弥陀さまの救いに出遇わせていただく法要としてお盆をいただきます。亡き方は、私が念仏の道を歩むきっかけをくださる大切な「導き手」です。
どうぞこのお盆、亡き方を偲びつつ、そのご縁を通して自分を見つめ、南無阿弥陀仏の救いを味わっていただければ幸いです。